
「逮捕されたら必ず裁判になる」「起訴されたらもう終わり」
刑事事件に対して、そんなイメージを持っている方も多いかもしれません。
しかし実際には、逮捕されたすべての人が裁判にかけられるわけではありませんし、起訴されずに事件が終わる「不起訴処分」という重要な制度が存在します。
このコラムでは、「不起訴とは何か?」「どんなケースで不起訴になるのか?」「弁護士にできることは何か?」といった疑問に答えるべく、刑事事件における不起訴処分の仕組みとその意義を解説いたします。
不起訴とは?

不起訴とは、検察官が「被疑者を刑事裁判にかけない(起訴しない)」と判断し、事件を終了させる処分のことです。
逮捕されたり取り調べを受けたりした場合でも、最終的に検察が不起訴処分とすれば、その事件について法廷に立つことはありません。
つまり、前科もつかないという点で極めて重要な決定です。
不起訴の種類
不起訴処分にはいくつかの種類があり、主に以下のように分類されます。
① 嫌疑なし
→犯罪が行われたこと自体に疑いがある、あるいは被疑者が犯人でないと判断された場合です。いわば「潔白が証明された」ケースであり、最も潔白性の高い不起訴です。
② 嫌疑不十分
→犯罪の疑いはあるが、有罪を立証するに足る証拠が十分にそろっていない場合です。無実であるとは言い切れないものの、有罪に持ち込むには根拠が足りないと検察が判断したケースです。
③ 起訴猶予
→犯罪が行われたことは事実と認定されても、被疑者が反省している、被害弁償が済んでいる、前科がないなど、情状が考慮されて「今回は起訴を見送る」という判断です。もっとも一般的な不起訴処分で、弁護士の働きかけによって導かれることが多いです。
起訴・不起訴の判断基準

検察官が起訴するかどうかを決める際には、次の2つの観点が重視されます。
1 公訴を維持できるだけの証拠があるか(立証可能性)
2 起訴が相当か(処分の相当性)
立証可能性とは、裁判で有罪判決を得られる見込みがあるかどうかという観点です。
証言や物的証拠、供述の整合性などを総合的に検討します。
日本では、無罪推定の原則があります。無罪の可能性が合理的にぬぐえない場合、有罪とすることはできません。
そのため、確実に有罪にできる証拠がない限り、起訴しないのが一般的です。
一方、相当性とは、社会的影響や被疑者の反省状況、被害弁償の有無などを踏まえ、「本当に裁判にかける必要があるのか」を判断する観点です。
すでに刑事裁判を行うまでもないほどの社会的制裁を受けていたり、被害者の方が許している状況であれば、裁判を行わずともよいのではないかという観点から、判断がなされます。
取調べ対応の重要性

不起訴を獲得するうえで、取調べ時の対応は極めて重要です。ここでの対応次第で、検察官がどう評価するか、起訴に進むかどうかが大きく左右されます。
● 取調べで気をつけるべきポイント
・無理に供述を合わせたり、迎合的な発言をしない
・虚偽の自白をしてしまわないよう冷静さを保つ
・黙秘権の行使も正当な権利である ・供述内容は記録に残り、後の判断材料になる
取調べは心理的な圧力が強く、長時間に及ぶことも少なくありません。そのため、事前に弁護士から適切なアドバイスを受けることが極めて重要です。供述の一言が起訴・不起訴を左右することもあるため、軽い気持ちで答えることは避けましょう。
● 弁護士の役割
弁護士は、取調べに対する心構えや具体的な対応について被疑者に助言します。
黙秘すべき場面と説明すべき場面を整理し、供述が不利な証拠にならないよう戦略的に対応を組み立てます。取調べが続く中でも継続的に接見を行い、精神的な支えとなることも重要な役割です。
弁護士ができること

刑事弁護人としての弁護士は、不起訴処分を目指して様々な活動を行います。具体的には以下のようなことが可能です。
・早期の接見により、警察・検察への対応方針をアドバイス
・被害者との示談交渉の実施
・反省文や謝罪文の作成支援
・被疑者の更生支援体制(就労、家族サポートなど)の提示
・検察官に対する意見書提出
・被疑者の社会的背景や生活再建計画を資料化して提出
・専門的な心理カウンセリングや社会福祉的支援を調整
このような活動を通すことで、不起訴を処分を獲得することにつながります。
まとめ
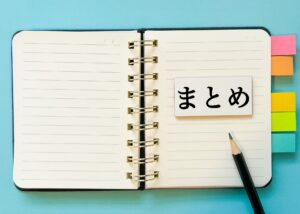
不起訴処分を目指すには、早期の対応と専門家の力が不可欠です。
刑事事件において不起訴処分を得ることは、被疑者にとって「前科が付かない」という極めて大きな意味を持ちます。
嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予といういずれのパターンにおいても、証拠・供述・情状など多くの要素が複雑に絡み合う中で、検察官が総合的に判断を下すため、専門的かつ戦略的なアプローチが不可欠です。
特に、取調べでの対応は不起訴の可否を大きく左右します。軽率な供述や誤った対応が不利な証拠となるおそれがあるため、早期に弁護士の助言を受けることが最も重要です。また、被害者との示談交渉や反省文の提出、就労や家庭環境の整備といった「更生支援」も不起訴処分に向けての大きな要素となります。
たとえ「一度の過ち」であっても、その後の人生を大きく左右することのないよう、まずは早めのご相談を強くおすすめします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。








